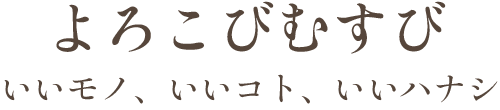今回お話を伺ったのは、現役の高校教師であり、鵠沼海岸で「学び」をテーマとしたコミュニティ団体とレンタルスペースを運営している新田里奈さん。不登校の問題に向き合ったことをきっかけに子どもを支える場所をつくる活動を始めたところ、保護者や地域の人の人生まで動き始め、活動は広がり続けています。
新田里奈さんプロフィール
学校心理士。湘南一ツ星高等学院(神奈川県藤沢市)学院長補佐。学びを通じて地域のコミュニティを繋ぐサークル『BE-GLOBAL』主宰。学びのスペース『BE-SPACE kugenuma』代表。私立進学校にて英語教諭として勤務後、フリーターを経て通信制高校教諭、そして現職に至る。教員の傍ら、親子の学び場、子どもの居場所、そして地域のつながる場づくりを目指し、地域のコミュニティ活動を始める。

――新田さんは本業が学校の先生ですが、どうして教員になろうと思ったのですか?
私自身、高校時代の経験が人生の軸になっているので、その大事な時期に関わる仕事につきたいと考えたからです。辛いこともうれしいこともたくさんあって、家族や学校の先生、地域の人たちの支えを感じた時期でした。
――地域の人たち…。具体的にはどんな人たちでしたか?
駄菓子屋さんとか、酒屋さんとか、習っていた空手の師範や先輩たちですね。いろいろな人の出会いがすごく励みになっていると年々感じています。例えば何か辛いことがあっても、外に出ると「元気にしてる?」と声をかけてもらえたりして、その時々の場所に集中すればそちらで頑張れる。そのような場所があることが支えになった経験から、場所を作りたいというのは根っこにあったような気がします。
――場所を作りたいという想いはいつ頃から持ち始めたのですか?
教職について10年ほど経ったころだと思います。教育現場での仕事に満足していたのですが、不登校の問題や、虐待、リストカット、援助交際、自殺願望など深刻なケースにも直面する機会が増えました。現場の教員としてできることには限界があり、経験不足や辛さを感じました。この子どもたちに誰かとの出会いがあって、ほかの場所を知ることができれば変わったのではないかという想いが生まれました。

――そして作られたのが、コミュニティ団体「BE-GLOBAL」ですね。
はい。友人に私の想いを話したところ、「やってみたら」と同じように教育に関心がある人を紹介してくれたのです。最初に活動を始めた3人とも英語を仕事にしており、広く世界を広げられるようにという願いを込めて「BE-GLOBAL」と名付けました。
――最初の活動はどんなものでしたか?
ダンスと英語を中心とした学習指導です。ダンスは学習指導要領で必修となっているのですが、体験したことがなければとっつきにくいので、少しでも経験のある子どもを増やしてあげたいと思いました。会場は公民館で、会費は先生にお支払いする分だけという活動でした。
――集客はどのようにしたのですか?
実験的に始めたので最初は口コミでした。ダンスはやってみたい子どもがすぐに集まりましたね。学習指導は体験会を何回か行い、仲良くなった子どもが継続してくれるようになりました。当初幼稚園生だった生徒さんが高校生になった今も来てくれています。これは学校や塾の先生にもないことなので、よかったなと思っています。要望にお応えする形でやり方を変えていく流動的な学びがBE-GLOBALのメリットです。
――一人ひとりの要望にお応えするのですね!
要望の数だけ先生がいるということです。先生と生徒はマッチングをしているのですが、今、教えたいという人は結構いらっしゃいます。BE-GLOBALの開始当初から、「先生も募集します」という情報は出しています。この場は教わるだけではなくて、お互いの「好き」を持ち寄って世界を広げようというコンセプトなので、賛同してくれる方が集まっています。
――究極のオーダーメイドですね。
そうですね。それができる場所にしたかったのです。いつも完璧にマッチングできるわけではなくて、試行錯誤の連続です。私は無理をして何かをするのは一番よくないと思っています。例えば塾は年会費や通う頻度など負荷かけすぎることがあると思います。最初は学びたいだけ学び、もっと学びたければもっと学べばいいと考えています。まずは入口になりたいのです。
私も母親なのでわかるのですが、今、保護者の方は子どもにいろいろなことをさせた方がいいと考えて焦っていると思います。そのことで子どもたちが学ぶことを嫌いになってしまうのが嫌だなと。とりあえずここに来て、体験して楽しいなと思えば別のところに行って学んでもいいし、ゆるく開催してくれている先生も多いので、そのペースで続けたいという人は続けていただければと思っています。

――先生たちもニーズに合わせてくれるのですね。
そうですね。主に作文教室をしていた先生が、雑誌作りに興味のある子どもたちのために雑誌チームを作って開講したり、読書会も開いたりしてくれています。
――最近は大人の方もいらっしゃるとか。
はい。先生が年上であるとは限らないです。サークル活動の方が先生を招くこともあります。先生同士のネットワークもできて、新たな教室を開く場合もあります。
――2019年に拠点として「BE-SPACE kugenuma」を開設されました。これはどのようなきっかけでしたか?
公民館で活動をしていましたが、「もっと学びたい」「もっと教えたい」という声が増えて、公民館の使用できる日数では足りなくなってきました。場所が必要だと思い始めていたときに、この場所が空いていることを聞き、見に来たら本当に良い場所で。

――不動産を借りるのには勇気がいりませんでしたか?
何も知らなかったからできたのでしょうね。仲間たちが「一緒にやってみよう!」と言ってくれたのが大きかったです。そして、この場の運営自体が、私にとっても「実践の学び」の場となると考えて決意しました。拠点(BE-SPACE kugenuma )の維持は大変ですが、多くの人が多くの体験をできるよう、学びの入口のハードルを下げたいと考えています。そのため基本的に講座は単発開催をメインとし、生徒さんがもっと学びたいという気持ちになったときに定期開催となります。
――運営における苦労や、その苦労を乗り越えられる理由を教えてください。
生徒さんや利用者様から入会金や維持費をいただいていないので、参加者が少ない時期には苦しいこともあります。それでも乗り越えられる理由は、やはりこの場所があるから生まれる出会いがあるからです。
――どのような出会いがあったのですか?
定年後を見据えて自分の力を地域で活かしたいと来てくださった人がいました。お話を聞いたところ将棋が教えられるとのことで、ボランティアで将棋の先生をしてくれて最近は生徒さんが増えてきています。教えるようになってから指導員の資格も取られて、最近は学童やカルチャーセンターなど活躍の場を広げられています。

また、最初は不登校の子どもたちにという想いで始めましたが、開設してみると大人が集まってきて、大人にも居場所が必要だということがわかってきました。お子さんに学ばせたい、と参加してくれた保護者の方には、自分が子どものときにやってみたかったけれどできなかったなど、ご自身の人生から生まれた想いがあります。子どもたちの成長を共に見守るうちに、「私も学びたい、やってみたい」という気持ちを話してくれて、学ぶ場につながったこともあります。親同士のお茶会や親子で英検にチャレンジする講座、自分探しワークショップなども開催しました。お子さんに不登校などの問題があるとお母さんが孤立してしまうことがあるので、保護者の方同士がつながってほしいと思っています。
――「BE-SPACE kugenuma」は大人がつながる場所にもなったのですね。
人は共通点があるとつながりやすいんですね。「BE-SPACE kugenuma」には、それぞれが「好き」を持ち寄っているのでつながりやすいです。特別なことでなくても、例えば開催した「子育てカフェ」では子どもが好き、子どもの未来を真剣に考えているという共通点がありました。お母さんたちはすごくパワーがあって、夢を持っていて刺激をいただきますね。

――2024年から始めた「学びラボくげぬま」というのはどのようなものですか?
「大人も子どもも 学びたいことを 学びたい時に」をテーマに学びたい時に学べる場所作りを目指しています。平日日中にでも学べるのが特徴です。不登校の問題が深刻化していますが、子どもたちに話を聞くと、子どもたちが行きたい場所とフリースクールが必ずしも一致するわけではないと感じています。中にはフリースクールは不登校生のいくところというイメージがあるので、自分は違うと考える人もいます。学校も先生も疲弊する中で、学びの選択肢は多くていいのではないでしょうか。不登校でなくても、今日は学びラボで学ぶという選択肢があっていい。ここには平日日中に子どもが来ても、「学校にいかなくていいの?」と聞く大人はいません。子どもも親も学校の先生も関わる講師も、みんなが幸せになる場所を目指しています。
――「BE-GLOBAL」「BE-SPACEkugenuma」を運営して感じる、一番の喜びを教えてください。

素晴らしい仲間との出会いです。「ビジネス」と完全に割り切った関係ではないので、直接の関わりがなくなってしまっても、この活動で出会った皆様は一生の仲間でいられるのでは、と思っています。大人も子どもも一緒に年を重ねていく仲間でいられるということが最大の喜びです。基本的にこの活動は皆が「好き」を持ち寄って動かしているので、それだけでも幸せな活動だなと思っています。今後はこれまで出会った人たちやこれから出会う皆様とともに学びながら、さらに発展して行けたらと思います。

<お話を聞いて>
「BE-SPACE kugenuma」の活動は、子どもたちはもちろん、教える人や保護者たちにも新しい一歩を踏み出すきっかけを提供しています。いろいろな人が「好き」を持ち寄る場を作った新田さんは「私はここの運営が好きなんです。好きだから続けています」と話してくれました。大切にしているのは、ビジネスとして利益を上げることよりも、たくさんの人と繋がりを作ること。高校教員、二人の子どもの母親という顔も持ちとても忙しい毎日ですが、今を大切に、世界を広げている姿は輝いていました。