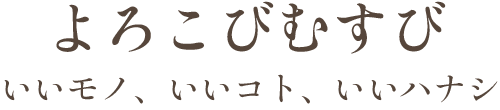今回お話を伺ったのは、グラフィックデザイン・クリエイティブ制作を中心に活躍している戸原貴子さん。たくさんの転機を乗り越えながら、キャリアを積み重ねてきた軌跡をお話しいただきました。
東京、赤羽生まれ
東京デザイン専門学校卒
印刷会社のデザイン部、企画デザイン会社を経て2012年独立、creative works Tane’t 設立
前年の東日本大震災を機に 同時進行でエコロジー関連のイベント制作にも参加
2015年出産を経て、子育て支援事業にも関わる
2020年デジタルハリウッドWebデザイナー専攻卒業、Web制作もスタート
2020年 関内イノベーションイニシアティブ株式会社のインハウスデザイナーを兼任
2022年 子育て女性の育児と自己実現の両立を支援する会社、株式会社オープンワールド主催のママ向けPhotoshop講座「まなんdeワーク」の講師をスタート
現在はお菓子メーカーのECサイトコンテンツ制作にも携わっている
ーー東京デザイン専門学校をご卒業ですが、学生時代からデザイン系に関心があったのですか?
大学附属の高校に通っていて、そのまま行けば4年制の大学にも行けたのですが、高校で勉強しているうちに、このまま進学することにピンとこなくなったことがきっかけです。早く社会に出たいという気持ちと、社会に出るにあたっては「ものを作る現場」に関われたらいいなという思いがあって、専門学校に切り替えて進学することにしました。
ーー「ものを作る現場」に関わりたいというのは、何か理由がありましたか?
学校でポスター描くとか、遠足のしおりの表紙を描くということが、とても楽しかったという記憶がありました。ノートをまとめるのも好きでした。勉強するというよりは、見やすくレイアウトをしたり、情報を整理したりすることが好きで。考えてみたら、そこが原点かもしれません。
ーーまさに今のお仕事につながっていますね。専門学校を卒業されて、印刷会社に入社されたのですね。
毎年専門学校から何人か行くという印刷会社に、専門学校の集団就職のような枠で入社しました。入社当初、社内で女性デザイナーは私だけでした。ハードな現場なので、女性には無理だろうと思われていたようです。新卒の時に担当したのは、紙をきりばりして版下を作る仕事でした。まだアナログの時代で、手書きで行っていました。
ーー手書きで…それは大変そうですね。
手書きのレイアウトは、現在の仕事の下地になっていると思います。それに、写植の職人やオペレーターなどたくさんの人が関わっていたので、締め切りや工程がしっかり決まっていて、むしろ昔の方がゆとりはありました。ちょうどアナログからMacに変わっていく過渡期で、Macの普及とともに手書きしたレイアウトをMacのオペレーターに渡して作ってもらうようになりました。自分でもMacが使えるようになるために、自分でパソコンや本を買って、勉強しながら仕事をしていたという感じでした。
ーー就職して4年目に転機があったと。
競合数社が参加した大手スーパーのクリスマスケーキのパンフレットのコンペに、私が出したデザイン案が選ばれて、撮影ディレクションから制作まで任されました。本社版のほかに、北海道版、近畿版など差し替え版を5、6冊同時進行で制作するので、会社としては大きな利益になるものでした。撮影指示なんてしたこともなかったのですが、それをやり遂げて意識が変わりました。
ーー大きな仕事だったのですね。どのように意識が変わりましたか?
会社も社運を賭けているし、カメラマン、フードコーディネーター、オペレーター、校正担当や営業担当など大勢の人が動いているし、責任が大きかったです。
たくさんの同じようなケーキの商品管理をして、背景やライティングを決め、撮影の順番を検討するなど効率の良い段取りをつける必要がありました。でも、そのような現場を仕切ることが向いていたような気がします。次に行った会社では、撮影の多い仕事をするようになりました。
ーー転職されたのですね。
もともといた会社からパートナー企業へ出向になったことがきっかけで、出向先にそのまま転職することになりました。転職先では、ファッションブランドの店頭のポップや家電やユニフォーム会社のパンフレットなどを制作し、クライアントの幅が広がりました。とにかく撮影現場によく行っていました。デザインも担当しつつ、そこに至るまでのロケハン、撮影現場決め、モデルのオーディション、ロケバスやお弁当の手配など、必要なことのすべてに携わっていました。
ーーそれはすごい仕事量ですね。
今考えるとよくやっていたな、と思います。徹夜もしていました。帰るように言われても、自分で納得いくまで仕上げないと帰れないと思っていました。
ーーその後、独立しようと思ったきっかけはどのようなものでしたか?
結婚したことがきっかけです。当時はメールチェックなども家でできなかったので、クライアントの返事を会社でずっと待っていなければなりませんでした。クライアントが夕方に回答してきて、そこから修正して期日までに仕上げなくてはならないとなるとどうしても夜に作業をすることになり、拘束時間が長くなります。
また、その頃自分の中で、「もっと違うものを見てみたい」という気分が高まっていました。音楽が好きで、フェスに行っていたのですが、そこで「ごみゼロ」などを目にするようになって関心が芽生え、代々木公園の「Earth Day Tokyo」のボランティアや「green drinks Tokyo」に参加したりしていました。そういう場所でいろいろなインプットがあって、これまではモノを売るということの手助けをしていたけれど、自分がやりたいことは本当にこれだったのかなと。デザイナーの仕事でなくてもいいから、いろいろやってみたいと思い始めました。
ーー「もっと違うものを見てみたい」という気持ちで独立されて、どのようなことをされていましたか?
前の会社の仕事を業務委託で受けながら、「earth garden」という団体の代表のお手伝いを始めました。ちょうど震災直後で、原発の問題などもあり、「国民が政治にもっと参加しなくてはいけないのではないか」「市民が対話して社会をつくりあげていかなくてはならないのではないか」という考えに共感して、エンジンがかかりました。小泉元首相などの著名人も登壇したトークイベント「せんきょcamp」の運営や、ウェブ、プレスリリースの制作を手伝ったりしていました。反原発デモの支援にもかかわったので、原発再稼働のタイミングでは取材も殺到し、そのメディアの受付をしたり、著名人のアテンドをしたり、歴史的な瞬間に立ち会ったような気がします。
ーーそのような活動に参加する原動力は、どこにあったのですか?
時代の雰囲気もあったと思います。その頃、よく言われていた「自分で暮らしは自分でつくる」という言葉にとても惹かれていました。それまでの与えられたものを受け入れるような社会が少しずつ変わってきていて、私自身も社会から与えられる仕事や暮らしがどれもピンときていなかったと気づき始めました。例えば、スーパーで食材を買うような、当たり前に過ごしている枠組みって、実は当たり前ではないのではないかと。「earth garden」での活動は2年ぐらいでしたが、本当にいろいろなものを見せてもらいましたし、そのときに感じた「自分の暮らしは自分のつくる」という気持ちは今も持ち続けています。
ーー次の転機はどのような時期でしたか?
出産した38歳のときです。20歳から38歳まで走り続けてきたので、1回真っ白にしたくて、制作の仕事もすべてストップしました。節目でしたね。子どもが1歳ぐらいのころから子育て支援拠点に行くようになって、そこで出会った人たちからチラシなどのデザインを頼まれるようになりました。仕事というよりは、ボランティアや少しの謝礼をもらうような形でしたが、何かを作れるのは楽しかったし、とても喜んでもらえてうれしかったです。
企業で働いているときは、地域との関わりはほとんどなかったのですが、子どもを通して繋がりができて、成長とともに広がっていきました。そこから、まちの小さな事業所や子育て団体の仕事を受けるようになり、まちの課題解決をしている人のお手伝いをしたいという想いが生まれてきました。小さな事業所や個人から仕事を受けるなら、ウェブサイト制作の知識も必要だと思い、スクールに1年間通いました。スクールに通ったことは人脈作りにもつながりました。
ーーどのようなネットワークができましたか?
当時、ママでも家で仕事ができるということで、子育て中の女性にウェブデザイナーという仕事が注目され始めていました。スクールで学ぶママたちと仲良くなって、一緒に何かできないかと話し合っていました。ママ達は、子育てで不測の事態が発生することもあり、一人では大きな仕事を受けるのは不安ですが、ウェブサイトの制作だったら分担も可能なのではないかと。そのときのキラキラした感じが印象に残っていて、クリエイエィブ業界、市民社会づくり、まちづくりに関わってきた経験を活かして、新しい働き方や生き方を見つけていきたいと思い、女性クリエイターのネットワーク「井戸端クリエイターネット」を立ち上げました。
ーー独立時につけた屋号「creative works Tane’t」にはどんな想いが込められていますか?
横浜トリエンナーレで見た日比野克彦さんの「種は船」にインスピレーションを得ています。種はその中に色んなものを記憶して、風に乗って違う場所でその記憶を花開かせる。Tane’tもお客さまの想いを制作物という「種」にしていろいろな場所に届けるお手伝いをしたい。という想いで名付けました。たね+ネットワーク=たねっと(Tane’t)です。
ーー「Tane’t」では、「でこぼこでいいじゃない」というキャッチコピーを掲げていますね。
例えば、商店街の中にチェーン店だけではなくて、いろいろな個性のあるお店があった方が楽しいですよね。商業的に儲からなくても、偏った想いを持っていてもいい、社会全体が「でこぼこ」の個性を許容しあい、リスペクトし合い、生きる価値、喜びを持てる社会になったらいいなという想いがあります。そのために、私はデザインでお客さまの個性が輝くようなお手伝いをしたいと思っています。
ーーどうやって個性を引き出すのですか?
対面で顔を合わせてその人の想いを受け止めて、最大限表現できるものを提案するようにしています。情報量をまとめたり、イメージを捉えたりするのは得意なのですが、こちらの押し付けになっていないかとか、相性とか難しさはあります。また、お客様の規模が少し大きくなると、ファシリテーションが必要になることがあって、そのようなスキルを磨いていく必要性も感じています。
ーー今後の目標について教えてください。
依頼内容として、スモールビジネスの方のブランディング全体を相談される事が多くなってきました。求められることが単なるデザイン提案だけではないので、理念やビジョンなどを一緒に整理していくために、さらなるコミュニケーション力やファシリテーション力を磨いて、良いものが作れるようになっていきたいです。いつまでも日々勉強です。やりたいことができるようになってきたので、今後はガンガン稼ぎたいですね(笑)。
<おはなしを聞いて>
「デザインは言葉でごまかして終われない商売」と戸原さんは言います。デザインするロゴやウェブサイトは愛着を持って長い間使っていただけるように、納得のいく答えを導けるまで考え続けるのだそうです。0から1を生み出す過程のプレッシャーで夜中に目が覚めることも。暮らしている間も目に入るものは全て見て考えているほか、新しい技術についてもずっと勉強を続けています。
独身時代に納得するまで企業で働き、結婚後は市民活動の世界、出産後は子育ての世界を見て、仕事や働き方を常にアップデートしてきた戸原さん。その広い視野と人をまとめる力は、デザインのみならず、プロデュース、ブランディングなどの幅広い活躍につながって、これからも私たちの周りを彩ってくれることでしょう。